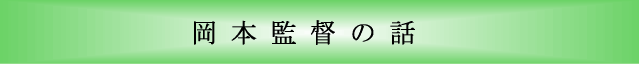 |
|
| 映画の岡本喜八監督が亡くなった。わたしの大好きな監督のひとりだった。かといって必ずしも忠実なファンだったわけではなく、いま改めて作品リストをのぞいてみても、数はそれほど多く見ていないことに気がつく。しかしいちばん技量を買い、いちばん評価していたという点では、実力ナンバーワン監督だったと思っている。興行的には不遇で、その力量が最後まで正当に評価されなかったきらいがあるのを、何よりも残念に思うのだ。 はじめて「独立愚連隊」シリーズを見たときの驚きはいまでも忘れられない。当時20そこそこ、まだ洋画一辺倒だった若造は、日本にもこんな痛快なアクション映画を撮る人がいるのかと仰天したものだった。ハリウッド製西部劇に一歩も引けをとらなかった、というより見せ方においてはるかに凌駕していた。しかも作品には明解なメッセージが込められており、単なる活劇映画ではない重みを見るものの心に残した。それが岡本監督作品に共通するサブテーマであったことにまもなく気づくが、その姿勢が最後まで変わらなかったことには限りない共鳴を覚えた。監督にとって映画とは、戦争で死んでいった仲間に対するレクイエムの場であったのだ。わたしなどそれによって力づけられた部分がいかに大きかったことか。こういう人がいてくれなかったら、とても生きてこられなかったようなところがある。晩年の傑作「大誘拐」の北林谷栄おばあちゃんには、いつまでも生きつづけてもらいたいのである。 このまえ黒木和雄監督の「父と暮らせば」を見てきたが、「美しい夏キリシマ」につづく3部作が見事に完結したことをいまもしみじみと思い返している。この黒木監督も、岡本監督と同じく戦争の傷跡を引きずりながら生きているひとりだ。時代がどう変わってしまおうが、その体験を抜きにしてものを見ることはできない。そういうこだわりを持つことでしか、いまの居場所を見つけられない人たち。わたしもその尻尾にくっついているひとりなのである。 岡本監督にお会いしたことはないが、まったく関係がないこともなかった。というのもどういう加減か、わたしの小説が目に止まり、映画化の候補の一端に加えてもらったことがあるからだ。たしか初期の「散る花もあり」だったと思うが、映画化権を一年間押さえさせてくれ、ということで岡本プロからお金までもらった。どうしてこの作品が、と思わないでもなかったが、わたしの作品のなかにある何かが、監督かスタッフの琴線に触れたのだろうと勝手に思い込んでいる。これまでテレビドラマになったものは少しあるが、映画になったものはない。自分の作品がもし映画化されるとしたら、岡本監督くらいお願いしたい人はなかった。だから声をかけてもらっただけですごく光栄に思った。あいにくその夢は実現しなかったが、いまでもそれは誇らしい思い出として記憶に残っている。 それにしても昭和が恐ろしい勢いで遠ざかりつつあるのを痛感する。去るものばかりが速くてならない。 心からのご冥福をお祈りしたい。合掌。(2005.2.20) |
|
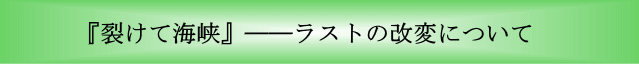 |
|
| 先月新装版として出た『裂けて海峡』がラストを改変したため本サイトで話題になってしまい、じつのところびっくりしている。そこであらためてここでその釈明をさせていただくことにした。 雑誌や新聞に連載したものを単行本にするときは、いつも大幅な書き直しや改変をしている。しかし以後は原則として手を入れない、というのがこれまでのわたしのやり方だった。作品というものはそのときそのときの作者の到達点のようなものだから、そのポイントはずらすべきでないと思っているのだ。それでなくともいまの時点で古い作品を読み直してみると、あまりにも下手でつたなくてうんざりしてしまう。できたら直したいのだが、直しはじめたらそれこそ際限がなく、最後は収拾がつかなくなってしまいそうで怖くなってくる。だからどうにも我慢できないところ、あらたに判明したミスや誤認、時代に合わなくなったところなど最低限の訂正はするが、大幅な改稿はしてこなかった。 今回もラストの1行こそすこし変えたが、ほかはほとんど手を入れていない。しかし最後だったからよけい目立ったようで、とんだお騒がせになってしまった。 では、なぜこういう風に直したかというと、じつをいうとはじめに書いたとき、こういう結末にしようと考えていたのだ。それを今回もとに戻したということである。べつな言い方をするとこの作品を書いて20数年間、ずっと直したいと思いつづけていた。それがやっと実現したということである。 この作品にはひとしお愛着があるし、自分でも代表作のひとつだと考えている。小説を書きはじめて2作目。処女作がいわばおずおずと手探りだったのに対し、これははじめから全力投球、自分のいちばん吐き出したかったものをストレートにぶっつけた作品だった。それこそ一気に書き上げたと記憶している。 その原動力になったものというと「国家に父親を殺された世代」に対する思い入れだ。それがすべてであり、わたしの出発点であり核なのである。一片の召集令状である日突然父親が戦場に狩り出され、ふたたび帰ってくることのなかった友だちがまわりなんとたくさんいたことか。彼らが戦後どのような辛酸をなめさせられたか、逐一見て知っているのだ。わたしもその世代の一員なのである。日本の経済成長を支えてきたのがその世代にほかならない。そのつらさや労苦が並大抵のものでなかったから、せめてその苦労を、わが子にだけはさせまいとなにも語らず黙って働いてきた世代なのだ。そういう彼らへのオマージュないしエールが、こういうストーリーになったということである。 したがって全体の構想が固まった段階で、「天に星……」からはじまる最後のフレーズはもうできていた。つまりラストの数行が先にあって、すべてがそれに向かって収斂していったといっていい。ただひとつ、南溟ということばがこの場合適切かどうか最後まで迷ったのだが、ほかのことばを見つけることができなかったのでそれで通してしまった。当初はここの一句一句をすべて改行し、全体で5行にするつもりだった。さらにもうひとつ、最初の扉に「世代を同じくする人へ」という献辞を入れたかった。 情けないことに、それをやれなかったのである。駆け出し作家のくせにカッコウのつけすぎじゃないかとか、体言止の羅列をなにか言われるんじゃないかとか、献辞を入れるほどの作品かとか、あれこれ考えているうち自信がなくなってしまい、最後はぐじぐじと思いとどまったのだ。最後のフレーズもはじめは「わたしは死んだ」で結ぶつもりだったのに、ここまで断定するのは書きすぎじゃないかとか、かえって誤解されるんじゃないかとか、迷うたびに段々追い込まれてしまい、とどのつまりが「わたしの死」という曖昧きわまりない、どうともとれることばで日和ってしまった。 それを20年間ずっと悔やんでいた。それこそぐじぐじと忘れることができなかった。それが今回、新版というかたちで生まれ変わることになったから、この際初心に忠実なかたちへ戻そうとしたのである。もうほとぼりも冷めたことだろうし、気づく人も少ないだろうからと、こっそり直して知らん顔をしているつもりだったが、それを鋭く指摘されたので作者としては少々狼狽し、あわてた。それでこういう弁明をする羽目になってしまったのだが、最後は作者にとってここは「わたしの死」ではなく「わたしは死んだ」でなければならなかった、ともうしあげるほかない。このような弁明で果たして納得していただけただろうか。お騒がせしました、といまは平謝りだが、もう改変するつもりはありません。(2004.9.11) |
|
 |
|
| キネマ旬報の昨年度ベスト1である。昭和20年の8月、つまり日本が太平洋戦争で無条件降伏をする直前の数日間を描いた作品だ。ありきたりの反戦映画だったら敬遠していただろう。反戦だとか反体制だとか、大義名分を振りかざした映画は好きじゃない。とくにその手の日本映画となると生真面目なばかりで笑いがなく、やたら怒鳴ったりわめいたり力んだり、見ていてほとほと疲れる。イデオロギーむき出しなのである。アジテーションにすぎないのである。ところがこの映画はちがうという。日本の片隅といっていい田舎の、ふつうの人たちの生活を淡々と描いているだけだという。だったらぜひ見てみたいと思った。 結論を先にいうと、見てよかった。こういう映画を見ることができてうれしかった。そしてこの映画がつくられるようになるまで50年という歳月を要したことに、戦後の日本がたどってきた道のりをあらためて思った。時代の成熟ということであれば遅きに失した感がしないでもないが、これは単にわたしの勉強不足ということかもしれない。この監督の作品を見たのははじめてなのだが、ほかにも長崎に原爆が投下される前の日の市民生活を描いた「TOMORROW /明日」という作品があり、今回の作品は3部作のうちの2作目にあたっているというからである。迂闊にもそのような映画があったことを知らなかった。つぎにつくられる3作目もふくめて、機会があればぜひ見たいと思う。 この映画は監督の実体験をもとにつくられている。終戦のとき15歳だった少年と、その周りにいた人々の物語である。15歳といえば中学生だが、すでに授業は行なわれなくなっており、学徒動員に駆り出されて飛行機製造工場で働いていた。その工場がグラマン艦載機によって攻撃され、機銃掃射を受けて何人もの級友が殺されてしまう。それを眼前にしながら助けることもできず逃げ惑った自分の卑劣さが、以後少年のトラウマとなって頭から片ときも離れない。その思いが、50年後にこの映画をつくらせたいちばんの動機になっているのだ。そのとき亡くなった11人のクラスメートへのレクイエムとしてこの映画は捧げられているのである。 その後少年は肺浸潤という一種の結核に侵され、郷里に帰される。映画が描いているのはキリシマの麓にあるその田舎へ帰ってからの数週間である。したがって画面に戦争の場面は出てこない。住民が受けている竹槍訓練だとか、兵士が爆薬を抱いて戦車の下に飛び込む特攻訓練だとかは日常的に行なわれているものの、それを除けば牧歌的といっていいおだやかな農村風景がひたすらひろがっている。連日のようにグラマン艦載機が、それもいまではキリシマより低い高度でゆうゆうと編隊飛行をしてくるが、住民のほうは慣れっこになって反応すらしなくなっている。広島に落とされた爆弾が新型爆弾らしいことも、数日前には長崎に落とされたらしいこともいまではみんなが知っている。 そこには格段の恐怖もなければ怒りもない。いつもと変わらぬ農村の暮らしがあるばかりである。それは無気力とか、あきらめとかいうのとはすこしちがう。なにもできないということである。前途にどんな不安や恐れが横たわっていようが、いまは目の前にある現実を受け入れるしかないということだ。なにかがわが身にふりかかってくるまでは、いまを精一杯生きていくしかない。みんなそうやって生きていたのである。この映画はそういうふつうの人の暮らしを、丹念に、細部までゆるがせにしないで描いている。当然テンポは遅いし事件らしい事件も起こらないのだが、退屈するとか長く感じるとかいうことはまったくなかった。主人公である15歳の少年と、自分の記憶とを引き比べて見ていたからである。映画を通して自分の過去を見ていたのだ。じつはこの映画のいちばんの眼目は、そこにあるといっていいだろう。いま60ぐらいから上の年齢に達している人は、映画を通していやおうなしに自分の過去を見てしまうのである。 わたしはこの映画をつくった黒木監督より5つ年下である。終戦のときが国民学校3年生、10歳だった。じつをいうとこの差がなんとも大きい。当時の15歳と10歳とでは、いまでは考えられないくらい大きな隔たりがあった。それは体験した量と受け取ることのできた情報量の差だといっていいだろう。学徒動員で狩り出されたということは、繰り上げ社会人にされたようなもので、おとなとして処遇されたことを意味する。10歳ではとてもそこまで望めず、基本的にはあくまでも子ども、一人前扱いはまったくされなかった。さらにいえば、そのとき就学年齢に達していなかった者はもっとちがう。なんの権利も義務も発生していない幼児という扱いでしかなかったからである。 したがってその差は身辺で起こる事態の受け止め方にそのままはね返った。ひとつの時代という時間的な普遍性こそあるものの、10歳ではそこに疑問や批判めいた思考の入る余地はまったくなかった。教えられたこと、聞いたことを鵜呑みにして、ひたすら頭につめこむだけ。実際そのころのわたしは大人の世界を懐疑的に見たことすらない。さらに年齢差ばかりか、地域差や経済差といったものもいまとは比較にならないほど大きかった。成人して以後のことだが、田舎で過ごしたわたしの戦時体験と都会で過ごした友人のそれとの間にあまりにも大きなちがい、というより同年齢でありながら共通点がほとんどないことにおどろいたことが何度もある。同じ年齢の学童だから同じ経験をしていたわけではけっしてなかった。社会がまったく閉鎖的だったのである。明治のはじまりからまだ80年しかたっておらず、農村の生活は江戸末期とそれほど違いはなかったのだ。ひと山越してしまうとことばから習慣までがらっとちがった。生まれ育った町や村の周辺から、一歩も外へ出ることなく一生を終える人が少なくなかった時代なのである。 終戦をわたしは山口県の日本海側にある小さな町で迎えた。片田舎だったという点ではこの映画の舞台となっている宮崎県とそれほど変わるところはない。しかし映画の少年が地主階級の家で、半自給自足経済だった農村ではかなり恵まれた暮らしだったのに対し、サラリーマン家庭だったわたしの家では食糧の調達がいつも最大の難問だった。一方でわたしの家にはゼネラルエレクトリックの扇風機があったし、庭にはブランコがあった。それでいて少年の家にあったフレームが斜めになった自転車には目をみはった。そんなハイカラな自転車など見たことすらなかったのである。 わたしの住んでいた町は、舗装道路こそなかったが国道も通っていれば鉄道も走っていた。港には漁港や市場があって人口5500人、半農半漁のほぼ平均的といっていい町だった。だが電話は町に20数台しかなかったし、車にいたっては父親の勤めていた工場にトラックが1台あるきりだった。靴(ズック)をはいている子はクラスに数人しかおらず、ほとんどが下駄か藁草履、雨が降ると草履が重くなって傷みが早くなるからか、男子ははだしで学校へくるものが少なくなかった。衛生状態が劣悪だったからトラホームにかかっている児童が多く、ひと夏が終わってみると流行り病や疫病でクラスのうち何人かが欠けていた。3年生までにわたしと机を並べていた少女ふたりがそうして亡くなった。町外れには隔離患者を収容するふだん無人の避病院があった。 アルミ製品はすべて供出させられたため弁当は握り飯。道路も片側半分は耕されて畑となり、川にかかるコンクリートの橋からはあらかた欄干がなくなってしまった。欄干や手すりを壊してなかの鉄筋を供出したからである。校庭は一部を残してイモ畑やカボチャ畑に変わり、炭焼き窯まで築かれた。2年生のとき学年を代表して『藁工品増産』というポスターを描かされた。工作の時間は、1年生のときはまだキビガラ細工ができたが2年生以降になるとそれも姿を消してしまい、あとはひたすら藁草履をつくらされた。藁だけはふんだんにあったからである。不器用だったから満足な草履は一度もつくれなかった。しかしおかげでいまでも縄だけはなうことができる。 大同小異、そのころの日本すべてが同じ状態だろうと思っていた。しかし単に個人的な、きわめて限定された記憶にすぎなかった。当時の日本がいったいいかなる状況にあったのか、広く、客観的にそれを説明できる材料をわたしは持っていない。ありていにいうと地域の差というより情報網の未発達や意志徹底の欠如、そこからくる不統一のために末端へ行くほどばらばらだったのではないかという気がしないでもない。いまでも当時を思い返すたび、なぜだか無性に腹がたってきてたまらなくなる。 それでもそういう日々が暗かったりみじめだったりしたことはけっしてなかった。それなりに明るく、日々希望に燃えていた。笑いや滑稽、卑猥さ、淫靡、あらゆるものがそろっていた。生きているということは、そういうことを周りから見つけ出すということでもあったのだ。それは追いつめられていたはずの戦争末期であれすこしも変わることはなかった。この映画はそれをきちんと描いている。いちばん高く評価したいのはその点である。 一方でこの映画が、われわれくらいの年代のものにしか訴求力を持たなくなっていることに痛切な空しさをおぼえた。若い人にはまず理解できないだろうと思うのだ。どれほど想像力を働かせてみたところで、この映画に描かれていることは想像力の埒外になってしまうだろう。歴史としてはもちろん、感覚としてもこういうことを理解できる土壌というものがいまでは完全に失われてしまったからだ。昨年「シカゴ」というミュージカル映画を見たとき、あとで若者が「なんであんなとこでいきなり歌い出すわけ?」としゃべっているのを聞いてびっくりしたことがある。はじめは冗談かと思った。「そうか。彼らの成長過程ではもうミュージカル映画というものがなくなっていたんだ」と気づいてやっと理解できた。わずか20年でそうなってしまうのだ。だったらいまの20代や30代に昭和20年という刷り込みがなかったとしても当然だろう。日本が戦争をしたことも、それに負けたことも知らない若者にこういう映画を見せたところでなんら伝わるものはないのである。理解せよと要求するほうが無理なのだ。それはわたしたちの親の世代がわたしたちにしてきたことであり、われわれがわれわれの子に対してしてきたことの当然の結果ともいえる。すなわち伝えるべきことを伝えてこなかった。この責任は限りなく重い。こういう映画をいろんな若者に見せ、そこから出てくるだろう突拍子もない感想を真剣に受け止める作業こそ、いまのおとなに必要ではないかと思うのである。 だれにでも必見の映画ですという薦め方はしない。あのころを振り返ってもう一度現在を考えてみよう、という人には機会があったらご覧なさいとお薦めする。 (2004.4.11) |
|
 |
|
| じつをいうとこの映画はパスするつもりだった。評判はよかったものの、話を聞いてみるといかにもゲテモノという気がしたからである。ところが年が明けてみると、昨年度のベストテンの洋画部門で高位にランクされているではないか。キネ旬ベストテンはもちろん、批評家の選出したリストでも中位に入っている。それなら見てみなければと考えを変えたのだった。 噂通りというか、面白い映画だったことはまちがいない。一方でゲテモノきわまりない映画であったこともたしか。見終わったあといちばん先に思ったことは、これまでのハリウッド製活劇から受けてきた感動とは、いったいなんだったのだろうかということだった。妙に釈然としなかったのである。ズールー族の反乱でもいいし、モロ族の反乱でもいい、セポイの反乱でもよければ、太平天国の乱でもいい、アメリカインディアンの反乱でもいい、この手の題材は繰り返し映画にされてきた。それをいつもはらはらどきどきしながら見てきた。ところがこの映画は日本が舞台になっている。自分たちの国であり、その歴史の末端にいまのわたしたちがいる。当然映画を見る目に余計なものが入ってくる。素直に感情移入することができなくて、いったいこれはなんなのだということになってしまったのである。 たかが映画だからこれでもいいか、と一旦は見逃してしまうつもりだった。ところがきのうテレビを見ていたら、どういう選出か知らないが、この映画が人気ベストワンを独走中といったコメントが出てきた。そして渡辺謙がゴールデングローブ賞やアカデミー賞にノミネートされたり「たそがれ清兵衛」が作品賞の候補になったり、海外からのニュースがぞくぞくと入ってくるにつれ、鼻高々になった日本側のはしゃぎぶりが尋常でなくなってきた。インターネットの書き込みをのぞいて見ても、感動した、すばらしい、と賛辞一辺倒なのである。それですっかり考え込んでしまった。こういう映画を高く評価してしまう日本人のメンタリティについて、余計なことながら一言いわずにはいられなくなったのである。 わたしに言わせたらたしかに面白かったが、それだけのこと。それほど高い評価の与えられる作品では断じてなかった。なぜって、まるっきりめちゃくちゃな映画ではないか。明治維新の時代に、関が原時代さながら、鎧兜に身を固めた武士団がガトリング銃に向かってバンザイ突撃をして全滅してしまうという話なのだ。それがなぜ武士道なのだ? わたしなどはサイパンやアッツ島や沖縄で繰り返されたバンザイ突撃を思い出していやな気持ちにならざるを得なかった。こういう散華を武士道だとか、日本人魂だとかいって賛美するのだけはやめてもらいたい。贔屓の引き倒しどころか勘違いもはなはだしい。死ぬことを恐れない勇気と、死なせ方の拙劣さとは本来まったく別個な問題なのだ。それを一緒くたにして、よかった、よかった、感動したでは、自己満足というよりばか丸出しの錯覚だろう。生き残っている人間の鉄面皮な欺瞞である。 竹槍で近代兵器に立ち向かう愚を、われわれは半世紀ほど前にいやというほど体験している。はなから勝負にならないものをさも勝負になるかのようにあおり、その根拠として持ち出されてきたのが大和魂とか、武士道とかいうものだった。もちろんこれは大和魂や武士道が悪いのではない。ことの本質をすり替える方便としてこれくらい便利なものもなかったということである。大事なことは、それをいとも簡単に受け入れてしまう土壌をわれわれ日本人はみな共有しているということなのだ。というよりわれわれ自身、追い詰められてしまうとそう言い出すにきまっているのである。そしてさらに追い詰められてしまうと、屈辱の生に甘んじるくらいなら名誉ある死を選ぼう、という結論にたやすく飛びついてしまうのだ。どんな屈辱にも耐えながら生きのびるための方策をあれこれ必死になって模索する、ということにはけっしてならない。潔く死のう、男らしく死のう、日本人らしく死のう、死のう、死のうの一点張りである。これは思考の放棄であり、生物として生まれおちてきた義務の放棄であり、生きるための努力の放棄でなくてなんなのか。生をまっとうするということは、本来その苦しみにあえぎながら生きつづけるということなのだ。その苦悩に耐えられなくて短絡的に死ぬことでもってお終いにするのは、もっとも卑怯な解決策だと思うのである。 さらにおどろいたことに、いろんな識者がこの映画の論評をしているが、わたしの見た限りすべてといっていいくらい、この映画の製作者が日本および日本文化、なによりも武士道に対して深い敬意を払っているとじつに好意的に受け止めていることだった。この映画が高い評価を得ている心象の大方がそこからきているのはまちがいない。欧米人が武士道に惹かれた、日本というものをやっと正当に評価しはじめた、といった島国根性の裏返しにすぎない日本人の自尊心をこれくらい心地よくくすぐってくれたものもなかったということだ。お人よしにもほどがある。わたしにはまったくそうは思えなかった。ここにあるのはいかにしたら日本人にこの映画が受け入れられるか、徹底的に考え抜かれたうえで練られた戦略でありその結果なのである。彼らが大いに努力したことはもちろん疑いない。しかしそれはあくまでもビジネスとしてであり、欧米で当たらなくても日本で大当たりすれば十分ペイする、というしたたかな計算によってつくりだされていることなのだ。だからこそトム・クルーズのような有名俳優を起用する必要があった。彼が武士道に感化され、生き方を変えてしまうところがいちばんの売りとなることまで計算されているのだ。アカデミー賞へのノミネートにしても、これで日本の評価がさらに上がることを見越して打たれた布石のひとつにすぎないとわたしは見ている。そういう意味では、日本という市場を徹底的に研究してつくりだされた最高の映画になっていることは疑いないのである。 渡辺謙がアカデミー賞を受賞することは多分ないだろう。この映画が欧米でさほどの評価を得ることも観衆を動員することもないだろう。武士道をもってするにバンザイ攻撃では、いくらなんでも特異すぎて万人の共感を得るわけにはいかないと思うからだ。わたしは新渡戸稲造の武士道を読んでいないから武士道についてはあれこれ言えないのだが、この映画でいえばカツモトが部下全員を道連れにバンザイ攻撃をかけて討ち死にしてみせるより、部下とその家族の安堵を引き換えに自分ひとり腹を切ったほうがはるかに男らしいし、そのほうがまだしも武士道に則っていたと思う。武士道とは死ぬことと見つけたりというのは、自分の身を犠牲にしてほかのものを助けるということが本義のはずなのだ。それだったら世界中の人にわからせる普遍性をまだしも持っていたと思うのである。 戦争とは究極のところ消耗戦である。単純に物量の問題にすぎず、その物量には人命も含まれる。量的に劣り、戦っても勝てる見込みがないとなればあらゆる手段をつくしても戦争は回避すべきであり、屈辱に甘んじてもひたすら忍従して再起の時をうかがうべきなのだ。自分たちの代でそれが果たせなかったら子孫に申し送るのである。いま生きているということは、のちに生まれてくるものより先に生きることであり、当然のちの者たちに責任を負う。どこをどうこねくり回してみたところで、バンザイ突撃を強制してお終いにしていい理屈が出てくるはずはないのだ。それがなんの疑問もなく受け入れられてしまうばかりか、かえって賛美してしまう日本人の国民性をわたしは徹底的に排斥したい。それでなくともわが国では量的不足を精神で補おうとするひどい欺瞞が日常的に横行している。バックアップ不足を棚に上げ、根性不足ということですべての責任を末端へ転嫁してしまうことが社会で、職場で、毎日のように行われているのではないのか。 その結果、小大を制すとか、柔剛を倒す、とかいったことがことさら高く評価される。柔道などまさにその幻想が神話になっている。しかし現実に小さいものは大きいものに勝てっこないのである。同程度の力のものが戦えば必ず大きいものが勝つ。むろんなかには例外もあって、弱いものが勝ってしまうこともまれにはある。ただそういうことはあくまでも確率の問題として処理すべきであって、10回に1回勝ったことを過大評価してもてはやすべきではない。その稀有を先例に10回に1回を3回に、5回に高めよというのは言いがかりでしかない。先の戦争で行われた特攻隊の攻撃をはじめ、日本軍の戦闘パターンをどうにも評価できないのはそういう自省がどこにもないからである。そもそも日本軍が正攻法で真正面から相手と戦ったのは日露戦争のときしかなかったのではないかと思うくらいなのだ。以後は近代になればなるほど、量的不足をごまかすための奇襲や不意打ち作戦のオンパレードになってくる。楠木正成以来の日本のお家芸、民族的伝統というわけだ。しかしアメリカ側の記録を見ると「日本軍は絶対に正面から攻めてこない」といったことがちゃんと書いてある。評価されているのではない。ばかにされているのだ。手の内がばれてしまえば奇襲などなんの役にもたたないのである。それを性懲りもなくこれでもかこれでもかと繰り返して自滅していった日本軍の救いのなさ。特攻隊攻撃などまさにその際たるものだろう。「敵の心胆を寒からしめた」とか「一矢を報いた」とか表現することにいったいどれだけの意味があったというのか。その程度の自画自賛のためにあれほど多くの若者を死に赴かしめたことを、われわれは日本人の心性の問題としてもっと真剣に考えなければならないと思う。重ねて言うが、死ぬことを恐れない勇気を拙劣な死なせ方で消費してしまうべきでは断じてない。 たかが映画に大げさなことばを並べてしまったが、人間の英知は時代とともに進化するわけではけっしてないことをこのごろ日々痛感している。若いときはもっと希望を持っていたし、もっと未来を信じていた。それがだんだんできなくなっている。しょせん人間は歴史から学べない生きものなのだ。過去の教訓を世代を超えてまで伝えることができないのである。そしてひとたび情勢が変わってしまうと以前と同じような光景が繰り返され、同じようなスローガンが氾濫し、だれもがそれを肯定するようになる。同じことを何回繰り返してもけっして懲りない。だがそれでも、いやちがう、われわれはもっと賢いはずだ、と信じて生きていくしかないのが人間なのだ。そういう苦悩を放棄するわけにはいかないのである。 |
|
 |
|
| このまえ禁煙について大見得を切ったので、この際それについて一席述べる。べつに格好をつけるつもりはないが、参考にしてもらえることもあるだろうと思うからだ。 作家にはヘビースモーカーがけっこう多い。わたしもそのひとりだったわけで、かつてはロングピースを1日3箱吸っていた。「ライトピース」などというものがまだなかったころの話だ。それがなんともうまくて、朝起きるとなにはさておき、せっせとコーヒー豆を挽いたものだ。そのコーヒーを飲みながら最初の一服をするときの喜びといったらなかった。世の中にこんなにうまいものがあるだろうかとそのつど思った。その煙草をぴたりとやめた。たいした理由はない。ちょうど禁煙時代に入りかけていて、タバコをやめるのがトレンドだったから、それなら自分もと思ったまでだ。単なる見栄。まあこれくらいわたしにふさわしい動機はなかった。 できなかったらみっともないので、事前には一切口外しなかった。できるとは思っていなかったというのがより正しい。あいつが禁煙できるならおれだってできるだろう、くらいの軽い気持ち。そして面白半分。この面白半分というのが、やめられたいちばんの要因だったのではないかと思っている。事実けっこう面白かった。したがって禁煙中つらかったとか、苦しかったとかいう記憶はほとんどない。これが健康に悪いとか、周囲の人に迷惑をかけるとか、正義感を振りかざしての禁煙だったらとても3日とはつづかなかっただろうと思うのだ。面白半分だからできた。面白半分だからそれがいまでもつづいているということである。したがっていつ吸うかもしれないし、また現にときどきは吸っている。それで正式には禁煙したと言ってない。休煙、ということにしてある。 そんなに簡単にやめられるのかと疑う人がいるかもしれない。しかしたぶん、だれにでもできる。原理は簡単きわまりない。要するに苦しまなければいいのである。考え方を切り替えるだけでいいのだ。 これまで何度か禁煙を試みたが、そのたびに挫折したという人に申し上げたい。1時間の禁煙だったら楽にできるんじゃありませんか。そのときの考え方に、ふた通りあると思うのだ。すなわち1時間もタバコを吸わなかったから苦しくて苦しくてたまらないという人と、あ、もう1時間禁煙しちゃった、なんだ、簡単じゃないかと思うことのできる人である。禁煙しようと思ったら後者の考え方がいいのはもちろんだ。 そしてそれが2時間もつづけば、えっ、もう2時間も禁煙したじゃないか、すごいすごい、おれってけっこうやるじゃないか、とますます面白がればいいのだ。2時間が3時間になり、3時間が4時間になればさらに面白くなる。1日ぐらいあっという間だし、1日禁煙できたらもううれしくてしようがないくらい面白さが加速してくる。それを2日3日と延長してゆくだけなのである。3日もやれば禁煙は半ば成功したようなもの。要は気持ちの持ち方、けっして深刻に考えてはいけない。たかがタバコだ。こんなものに悩んだり強迫観念に駆られたりするのがそもそもおかしい。 だからたとえ途中で挫折してしまったとしても、それはそれでかまわない。そういう弱さを併せ持っているのが人間なのだから。やっぱりおれはだめだ、なんていう風には考えない。今回は5日禁煙できたから、つぎはもっとできるんじゃないか、という風に考えていつかまたその気になったとき再挑戦してみたらいいのだ。禁煙なんて簡単だということがだんだんわかってくるだろう。つまり禁煙と仲よくなってしまえばいい。前向き、後悔しない、楽天思考、そういう頭の切り替えがいちばん大事だと思うのである。 いまでも完全な禁煙をしているわけではない証拠に、年に何回かは吸っている。たとえばパーティなどに出て、そのあと2次会3次会に繰り出して騒ぎいだりするとき、酒の勢いを借りて「おい、1本くれや」ともらって吸う。もちろんできたらロングピースがいい。ありがたいことに作家仲間にはかなりピース党がいるのである。 それで1本吸ってみるのだが、これがじーんと感涙にむせびそうになるくらいうまい。一口吸うだけで瞬間的に世界が変わってしまうのだ。くらくらっと目が回り、頭のなかが空っぽになってしまって、目の前がふわーっとぼやけてくる。それもバラ色。人生にはこんなにすばらしい境地があったのか、という気持ちにさえなる。そしてひょっとすると、おれは人生最大の楽しみをドブに捨ててしまったんじゃないか、と後悔したくなる。 ただしこのとき吸えるのは、ロングピースだと2口までである。強烈すぎてそれ以上吸うと気持ちが悪くなってしまう。つまり再喫煙は1口に限る。またそれくらいでやめておいたほうが、リバウンドせずにおさめられる限界かもしれない。 それと、思わぬ副作用がある。それは1口吸っただけで口のまわりがいっぺんにヤニ臭くなり、なんとも不快で不快でたまらなくなってくることだ。その場で口をゆすぎたくなるし、磨けたら歯を磨きたくなる。タバコを吸わない者や禁煙者にとって、タバコのヤニの臭いというものがいかに不快なものか、はじめて実感できるのである。タバコを吸っていたときは絶対気がつかない臭いでもある。こういう臭いとおさらばできただけでも、タバコをやめてよかったということが改めて認識できるのである。 禁煙運動に携わっている人たちの話を聞いてみると、禁煙に成功したのちも、好奇心半分、つい1本吸ってみることを厳にいましめている。たった1本でもとの木阿弥に戻ってしまう人がじつに多いらしいのだ。そういう面があることはたしかに否定できないと思う。禁煙すればするほど、つぎの1本のうまさが増してくるように思えるからである。わたしの場合も10年近くは完全禁煙してその間一本も手を出していない。そののちになって試してみたもので、べつの言い方をすると、いま1本や2本吸ったからってけっしてもとには戻らないという自信があるからこそ吸っている。というより吸って見せているといったほうがいいか。これも要するに人前での見栄なのである。 ついでに白状しておくと、禁煙して3年くらいは夢の中でうっかりタバコを吸ってしまい、しまったとばかり目を覚ましたことが何回もある。タバコを吸いたいという願望がそれほど潜在意識として残っていたのかと思う。だから禁煙しようと思ったら、やはり当面は完全禁煙するべきだろうなと思う。そのうえの境地まで達したとき、ここではじめて、1本や2本吸ったくらいでもとに戻れるものなら戻してみろ、という誘惑とたたかう楽しみもできてくるのである。 いまのわたしは喫煙者に一片の同情もしてやらない絶対禁煙主義者である。タバコの煙が流れてくると露骨にいやな顔をするし、初対面でいきなりタバコを吸いだすような編集者だったら絶対に仕事をしないことにしている。レストランに入ってもタバコのヤニがこびりついているような店とか、禁煙席がなかったりする店とかだったら腰を落ち着けていてもその場から出てくる。だいたい煙草は安すぎる。1箱4000円くらいの値段にすべきだと思っている。それでも吸う人は吸うだろうし、そんなに高けりゃやめる、という人が出てきてもそれはそれでけっこう。すくなくともそれくらい高価になれば、歩きタバコやポイ捨てがなくなって街がきれいになり、喫煙者のマナーがよくなることはまちがいない。 いざ臨終というときには煙草を吸わせるように、家族には早くから申し渡してある。そのとき吸うピースはどんな味がするだろうか。それを想像するだけでもやめた楽しみがあるというものである。 |
|
 |
|
| このまえ、メールプラザにJOLLY JOKERさんから映画についての投稿があったので、今回はその話を受けて映画についてすこし書いてみよう。 前にも書いたことだが映画は比較的見ているほうである。近くにシネマコンプレックスがあり、常時11本の映画が上映されているからだ。夜の9時すぎからでも見に行くことができる。そういう足場のよさと、1000円ぽっきりというシニア料金はなんといってもありがたい。本と映画しか楽しみがない人間にとって(嘘をつけ、という声があるかもしれないが)つくづくいいところに住んでいると思うのである。 しかし最近は映画に対して以前ほど心がときめかなくなった。おもしろい映画はたしかに多いのだが、いつまでたっても忘れられない映画、しみじみとした余韻があとあとまで残る映画、見るたびに新たな感動や発見をおぼえる映画、落ち込んでいるとき勇気づけられたり慰められたりする映画は、もう絶滅したか、絶滅寸前になっているといってまちがいないように思う。映画にそういうものを求めること自体がもう古臭くなっているのかもしれない。しかしわたしは映画というものはイマジネーションの世界でなければならないと固く信じている人間のひとりなのだ。映像は単なるその表現手段にすぎず、観客がその映像からさまざまなイマジネーションをつぎつぎふくらませられる映画こそ、真に映画と呼ぶにふさわしい映画だと固く信じているのである。 ところが最近の映画は、それを見る側のイマジネーションではなくてつくる側のイマジネーションの問題だと勘違いしているみたいなところがある。人をあっとおどろかせる想像力の極地みたいな映像をつぎつぎにつくりだしはするものの、見るもののイマジネーションがそこからどれだけ飛躍できるかといった要素にはまったく考慮が払われていない。つくりだした映像にイマジネーションを隷属させてしまおうとしているとしか思えないのである。当然つぎからつぎへと新手奇手を繰り出し、目先を変えることに汲々としてそのテクニックばかりが進化することになる。昨今の映画が退廃ないし退化の一途をたどっていると思ういちばんの理由がこれだ。映像表現の黄金期ともいえた時代は終わり、ふたたび活動大写真のむかしに舞いもどってしまった。昨今の見世物映画のオンパレードを見るにつけそう思えてならないのである。 始末が悪いのはそれでときたまお化けのように大当たりする作品が登場し、業界が一時的にせよ活気づいたかに見えることがあることだ。結果としては2番煎じ、3番煎じみたいな作品が市場にあふれ、最後は尻すぼみに終わって業界の衰退化に拍車をかけてしまうことになる。その点では最近の出版界とまったく同じ。出版不況が加速すればするほど売れ筋の本が何百冊も平積みされ、一見目もくらまんばかりのはなやかさをつくりだしている。しかしこれは見せかけの繁栄にすぎず、いずれ返本の山となってわが身に降りかかってくるはずで、はっきりいって末期症状特有の現象に他ならない。こうなったらもう行きつくところまで行くしかないだろうとわたしは思っている。出版社がばたばたつぶれ、作家がめしを食えなくなったとき、やっとそれで新しい状況が生まれてくる条件が整うと思うのである。 ちょっと脱線しすぎたかもしれないが、映画もかつては大作、小品、味のある作品がそろってじつにバラエティ豊かだった。練りに練った脚本、達者な監督、一癖もふた癖もある役者、三者がそろってつくりあげた、つまり職人たちの腕の冴えみたい映画を存分に堪能することができた。そういう職人芸みたいなものがなくなってしまった。しかしこれはなにも映画人の責任ではなく、職人というものの存在を必要としなくなった時代相が反映されているだけかもしれない。社会がそれくらい変わってしまったのである。 先月2番館で「アバウト・シュミット」を見たのだが、これは夏に封切られたとき忙しくて見落としてしまった映画だった。たまたま2番館に出てきたから見ることができたが、こういうことはむしろ例外。昨今は封切られたとき見ておかないともう見る機会はないに等しい。2番館とか名画座とかいったものの数が減り、再上映される映画がきわめて少なくなっている。だいたい名画座そのものがもう商売にならなくなっているのだ。札幌でもこの夏以来3つの映画館が廃業してしまった。おそらくいまの若い人は満員の映画館で映画を立って見た経験などないだろう。地味な映画になるほど客はぱらぱらとしかいないのが実情だ。とくに壮年以降の観客はほとんどいっていいくらいいない。 映画館に行かなくてもテレビやビデオやDVDなど見るものはいくらでもある。映画自体公開されて数ヶ月もすればもうビデオ化されてしまうから、それを見れば同じだという人がいるかもしれない。しかしわたしはそういう人の感覚を信用しない。映画はやはり映画館で見るべきものである。わたしはビデオやDVDをほとんど見ないが(ほんとは自宅にその設備がない)明るいところと暗いところで見るものには本質的なちがいがあると思っている。映画の魅力は明かりが消えて館内が暗くなり、さあこれから映画がはじまるというときのあのわくわくする一瞬にある。ビデオやDVDはしょせんテレビの延長でしかない。明かりのついた部屋でお茶を飲みながら、菓子をつまみながら、ときにはかみさんの相手をしながら見るのでは、感情移入のしようがないではないか。映画は絶対に映画館で見るべきものなのだ。 とこんなことをいえば、自分がいかにコケの生えた古いタイプの映画ファンであるか、もう明らかだろう。しかし映画とはそういうものだと信じている以上これはもう変えようがない。スクリーンは夢のつづきであってもらいたいし、またそういう夢を見させてくれるものでありつづけてもらいたいのだ。だからビートたけしに八つ当たりするわけではないが、彼のつくった映画は見たことがないし、これからも見ることはないと断言する。さあこれからたけしの映画がはじまるからといって、胸がわくわくときめきますか。テレビのスイッチを入れさえすれば出てくるたけしはまさに日常性そのもの。映画というものは非日常の世界でなければならないと信じているわたしとは断じて相容れないのである。 繰り返して言う。映画が真に映画らしかった時代はもう終わってしまった。もちろんそれでもまだわたしは見つづけるだろうし、この先も見放すことはないだろう。それくらい映画が好きだし、未来に希望も託しておきたいからだ。過去を振り返ってみても、いまの自分が若いとき見た映画からどれだけ多くのものを授かっているか、映画というものがなかったらいまのわたしはなかったといってけっして過言ではないのである。大のご贔屓だったジョン・フォード、ビリー・ワイルダー、ウイリアム・ワイラー、アルフレッド・ヒチコック、黒澤明といった作家たちの黄金時代をリアルタイムで経験させてもらったことがいかにしあわせだったことか、運よくその時代に生まれ合わせたことをこよなくうれしく、誇りに思っているのである。 |
